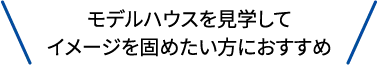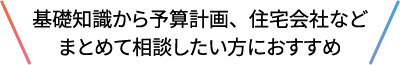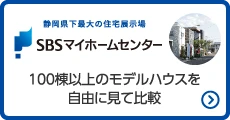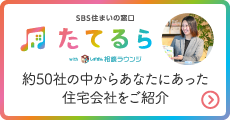木内菜穂子
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
この記事では、健康被害が出ないように自然素材を利用したいと考えている方に向けて、健康住宅の自然素材の種類や特徴、選び方などについて解説します。自然素材は、身体にやさしいだけでなく快適な住空間のためにも役立ちますので、ぜひ参考にしてください。
住宅を建築する際には、ハウスシック症候群といった健康被害が出ないように、自然素材を利用したいと考えている方もいるでしょう。特に、小さな子どもや高齢者がいる世帯では、自然素材に興味を持っている傾向にあります。
自然素材は、身体にやさしいだけでなく快適な住空間を実現できたり、長期間にわたり住み続けられたりするメリットもあります。
本記事では、健康住宅の自然素材の種類や特徴、選び方などについて解説していきます。
健康住宅づくりの自然素材の選び方
住宅に、アレルギーに配慮した自然素材を選ぶと、健康的で快適な住空間を実現できるでしょう。
健康に配慮した住宅づくりのためには、使用する素材の特性やメリット・デメリットを理解したうえで、住む人のライフスタイルに合ったものを選ぶことが大切です。部屋ごとに適した素材が異なる点にも注意しましょう。
また、自然素材は一般的な材料よりも高額になる傾向があるため、予算内に収まるように調整する必要があります。
どの自然素材を選ぶかによって、将来の住み心地や住宅全体の雰囲気に影響するため、素材の触り心地や色味、デザインなどの面でも満足のいくものを選ぶと良いでしょう。耐久性のある素材を使用すれば長期間住み続けられ、環境に優しいサステナブルな暮らしが可能です。
健康住宅によく使われる自然素材の特徴や、場所別におすすめの自然素材をこの後ご紹介します。
健康住宅の自然素材の特徴
健康住宅は、シックハウス症候群の原因となる化学物質を最小限に減らしており、住む人の健康に配慮しているという特徴があります。
一般的な住宅用建材には、シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドが含まれていることが少なくありません。接着剤や塗料などに含まれる化学物質が、アレルギーやアトピーなどの原因になる可能性があるのです。
こういった化学物質をできるだけ使用しない自然素材の住宅での生活は、化学物質に敏感な方や子育て世代などにとっては、特に安心感があるでしょう。
さらに、自然素材にはリラックス効果があるため、疲れた心を優しく包み込み、安らぎを与えてくれるだけでなく、集中力を高める効果も期待できるといわれています。
代表的な自然素材の種類と特徴
住宅に使われる自然素材には、珪藻土やタイル、石材、無垢材などさまざまな種類があります。主な素材ごとの特徴を確認していきましょう。
珪藻土
珪藻土とは、植物プランクトンの一種である珪藻の死骸が海や湖の底に堆積し、化石になったものです。「調湿性」があり、湿度が高いときは吸湿し、乾燥しているときは放湿することで、人体に快適な湿度(50〜60%程度)を保ちます。結露防止にも効果的です。
断熱機能も高く、冬は暖かく夏は涼しく保ちやすいため、エネルギー使用量を抑えられます。
なお、乾燥によりひび割れが発生しやすい点には注意が必要ですが、軽いひび割れなら自身で手入れ可能です。
タイル、石材
タイルは、変色・変質・劣化が少ないうえ、熱・水・火にも強いため、お手入れがしやすい素材です。吸水率によってⅠ類(磁器質タイル)、Ⅱ類(せっ器質タイル)、Ⅲ類(陶器質タイル)の3つに分かれます。また、内装や外装、床など、利用する場所により、それぞれ適したタイルがあります。
石材は種類が豊富なため、好みに応じたデザインを選ぶと良いでしょう。床に石材を利用すると、硬度があるため木材よりも傷がつきにくく掃除がしやすい点がメリットです。ただし、重く固いものを落とすと割れやすいことや、熱伝導率が低いため冬場は足元が冷えやすいといったデメリットもあります。
無垢材
無垢材とは、接着剤を利用せず、自然の木をそのまま切り出した未加工の木材のことです。高い調湿機能があり、室内の湿度を吸収・放出することで適度な湿度を保ちます。
無垢材は適度な弾力があり衝撃を吸収するため、フローリングに利用すると膝への負担を軽減できます。断熱性が高いことや肌触りが良いといった特徴もあり、快適な住み心地を実現してくれるでしょう。
無垢材は、湿度の変化に反応して伸縮するため、施工直後は多少の凸凹やすき間が生じることがあります。しかし、これは無垢材の特性であり、欠点ではありません。適切なメンテナンスを行いながら、自然素材ならではの変化を楽しみましょう。
コルク
コルクは、コルクガシの樹皮のコルク組織を剥がして加工したもので、板状に圧縮した床材をコルクタイルといいます。表皮のみを利用するため木を伐採する必要がなく、再生可能な素材として、環境保護の観点からも優れた素材です。
細かい気泡があり空気を含んでいることから、弾力性・防音性・防水性・調湿性・断熱性が高いです。足腰に優しく、素足で歩いても温かみがあります。
天然リノリウム
天然リノリウムとは、亜麻仁油や石灰岩、木粉などを混ぜ合わせて作られる素材です。
有害物質が発生しないためハウスシック症候群対策に役立つほか、抗菌作用があり家族をウィルスから守る効果があります。また、耐火性が高く、傷やへこみが付きにくいという特徴もあります。
ただし、形状が似ている一般的なビニール製の素材と比較して、高額な傾向があることや、亜麻仁油の独特なにおいが気になる方もいることに注意しましょう。
畳
畳は、いぐさや藁などを原料とした自然素材です。
いぐさの中には多数の気孔があり、内部に空気を含みやすいため、保温性や断熱性に優れています。また、気孔の内部にシックハウス症候群の原因となる有害物質を吸着してくれることから、室内の空気を清浄化する効果もあります。
素足でも優しい踏み心地で、いぐさ独特の香りでリラックス効果も期待できます。
ただし、湿気に弱くカビが生えやすいことや、経年により変色や日焼けをするといったデメリットも覚えておきましょう。
漆喰
漆喰は、水酸化カルシウム(消石灰)を主成分とし、麻すさや海藻のりなどを混ぜて練り上げた壁材です。水酸化カルシウムは、サンゴ礁が時間をかけて変化したもので、身体に優しい素材とされています。
漆喰は二酸化炭素を吸収することでより硬度を増すため、時の経過に伴い耐久性が向上します。また、不燃性なので高い耐火性がある点もメリットです。
ただし、漆喰壁は手間や時間がかかるため高額な費用がかかります。また、ひび割れが生じることがあるので多少手入れが必要です。
ホタテ漆喰
ホタテ漆喰は、ホタテの貝殻を主な原料とした漆喰です。ホタテの貝殻の光沢を活かした、上品できめ細かな質感が魅力です。
ホタテ貝は多孔質構造となっているため、調湿性や消臭性に優れています。室内の湿度により吸湿や放湿を行い、空間を適度な湿度に保てるうえ、カビやダニ予防にも効果的です。自然素材であるため、ハウスシック症候群防止にも役立ちます。
一般的な漆喰と同様に、高いコストがかかることやひび割れが発生するといった点がデメリットです。
和紙
和紙は、楮(こうぞ)・雁皮(がんぴ)・三椏(みつまた)などの植物が原料となる伝統的な自然素材です。以前は障子やふすまなどに利用されてくることが多くみられましたが、現在は壁紙としても利用されています。
和紙の繊維質が日光や照明を乱反射させることで、柔らかい明かりでリラックスできる空間づくりができます。紙には保温性があるため、室内の温度を一定に保ちやすいことや、吸音性により音漏れ防止にも効果的です。
ただし、和紙は大量生産ができないため、価格が高くなる傾向があります。
【場所別】自然素材のおすすめ素材
キッチンやリビングなど、場所によっておすすめの自然素材が異なります。それぞれの場所に適した素材を確認していきましょう。
リビング
家族が集まる空間であるリビングは、特に自然素材にこだわりたい場所です。
壁には、珪藻土・漆喰・ホタテ漆喰などがおすすめです。いずれも、ハウスシック症候群対策がとれるほか、調湿性や断熱性、耐火性に優れています。
床には、杉・ヒノキ・コルクなどがおすすめです。杉やヒノキには吸音性や衝撃吸収性があるうえに、リラックス効果のある豊かな香りが魅力です。コルクも防音性が高く、滑りにくいという特徴があります。
キッチン
キッチンに利用する自然素材は、防水性や吸湿性にこだわると良いでしょう。珪藻土や漆喰は調湿性や耐火性に優れているため、水回りにおすすめの素材です。
床材としては、ヒノキやタイル、コルクなどが向いています。リビングとのバランスを取りたい場合はヒノキを、防水性や掃除のしやすさを優先するならタイルが良いでしょう。コルクは、耐水性に優れており滑りにくい点が特徴です。
また、ワークトップ(天板)には天然大理石を利用すると高級感が出せますが、コストを抑えたい場合はタイルを検討しても良いでしょう。
浴室・トイレ
浴室やトイレにといった水を使う場所では、耐湿性や調湿性に優れた自然素材を選ぶことがポイントです。
珪藻土には調湿効果があり、漆喰には消臭効果があるので壁材として良いでしょう。ヒノキの一種である「サワラ」は、高い防水性や防湿性があるうえに、ダニを防止する効果があるため、水回りに向いている素材です。
ほかにも、タイル・天然リノリウム・石材を利用するのもおすすめです。デザインやお手入れのしやすさなども考慮して選びましょう。
和室
和室であれば、いぐさや藁などの天然素材を利用した畳がおすすめです。保温性や断熱性があるほか、有害物質を含まないため快適な空間作りにも役立ちます。また、リラックス効果や鎮静効果がある点も見逃せません。
壁は、保温性や吸音性のある和紙や、調湿性や断熱性のある珪藻土などを選ぶと良いでしょう。使用する木材は、衝撃や腐食に強いケヤキや、耐久性や抗菌効果があり独特の香りを楽しめるヒノキなどがおすすめです。
健康住宅の自然素材を長持ちさせるメンテナンス
健康に配慮した自然素材で作られた住宅は、メンテナンスが大変というイメージがあるかもしれません。確かに、メンテナンス上の注意点はいくつかありますが、ポイントを押さえて行えば難しくはありません。
通常の住宅のメンテナンスとそれほど変わらないと考えて良いでしょう。ただし、素材ごとに適したケアを行う必要があります。それぞれの素材ごとに、手入れのポイントを解説します。
漆喰の手入れ
漆喰はほこりがつきにくいという性質がありますが、白色だけに汚れが付くと目立ちやすいです。汚れたときは、消しゴムで軽くこすると落ちることがあります。落ちない場合は、メラミンスポンジを水に濡らして薄く削ってみましょう。
飲み物やマジックなどで汚れた場合は、漆喰に色素が沈着してしまうため、サンドペーパーで優しく表面をこすってケアしてください。
珪藻土の手入れ
珪藻土のお手入れも、基本的には漆喰と同じように行います。まずは消しゴムで試し、落ちなければメラミンスポンジでケアしてみましょう。
それでも落ちないシミには、中性洗剤を薄めたもので優しく拭き取るなどして、早めに対処することが大切です。
また、小さなヒビであればご家庭で補修が可能です。漆喰を水で溶いたものを指や柔らかいスポンジなどで塗り込むか、霧吹きで水を吹きかけヒビ割れ部分をならします。乾燥すると、ヒビのない元の状態に戻ります。
無垢材の基本的な手入れ
無垢材のお手入れは、ほこりを掃除機で吸い取ったり、乾いたモップでの乾拭きが基本です。水分に弱いという性質があるため、雑巾やモップを水に濡らして掃除することは控えましょう。
それでも汚れが気になるときは、水を十分に絞った雑巾で拭いた後に乾拭きします。しつこい汚れの場合は、中性洗剤を水に溶かしたものでも構いません。
つや出しをしたいときは、ワックスやオイルなどを塗るのもおすすめです。ただし、当初から塗装されていたものと同じものを使用してください。
無垢材の傷の手入れ
無垢材の床がへこんだり傷がついたりしたときは、家庭用のスチームアイロンを利用してお手入れできます。直したい部分に湿らせた薄い布を置き、スチームアイロンをかけると、木の繊維が膨張することで、へこみや傷がなくなります。
表面がざらざらしたり膨らんだりした場合は、サンドペーパーで優しく削ると滑らかになるでしょう。
健康住宅の自然素材は特性を活かした選び方を
自然素材を利用した健康住宅は、家族の健康を守るだけでなく、快適な住空間の実現に欠かせないものです。素材一つひとつの特徴やメリット・注意点などを知り、場所ごとに適したものを選びましょう。
定期的にメンテナンスをすることで、長い年月住み続けることが可能です。時間の経過とともに馴染んで、美しく変わっていく過程を楽しめるのも自然素材の醍醐味の一つです。